No-16 認識の段階
※ ここに掲載してある文章は、日本共産党発行の「月刊学習」誌に、1970年代、3年以上に渡って掲載されたものの転載です。管理人によるオリジナルでは有りません。
トップページを参照のこと。
1、認識の感性的段階と理性的段階
この講座の第14回に、外界(物質)を反映するという意識の機能(働き)のなかで、感覚や意志から認識を区別する特徴として、
- 認識は客観的事物・事実を客観的に(ありのままに)反映しようとするものであること、
- 認識は必ずしも常に客観的事物・事実をありのままに反映しているとは限らないが、しかし常に、客観的事物・事実をありのままに反映しようとする努力をしており、この理想に少しでも近づこうとしているものである
ということを述べました。 そして、
- 左手を氷水に、右手を熱い湯に数分間浸していてから、両手をぬるま湯に入れると、左手は暖かいと感じ、右手は冷たいと感じるというようなおかしなことがおこるが、そのぬるま湯に温度計をつっこんでその目盛りを目でよみとれば、ぬるま湯の温度を正確に知る(反映する)ことができる、という実例をあげて、人間の皮層に備わっている温度感覚器官は物体の温度を大体知ることはできても、正確に知ることができないけれども、温度計を用いればこれを正確に知ることができる、つまり、人間は客観的事物・事実を正確に反映するためにいろいろな工夫をしてきたのであって、温度計を用いるということはその工夫の現われの一つである、
と言うことを述べました。
この例で示したように、皮膚に備わっている温度感覚器官だけを頼りにして物体の温度を熱いとか冷たいとかいうように反映しているのが、感性的段階における認識であり、これに対して、温度計を用いて物体の温度を、例えば25度であるとか32度であるとかいうように反映するのが、理性的段階における認識です
「感性的認識」
感性的段階における認識は、人間が、感覚器官を持っている人間以外の動物と、共通に持っている認識だといえます。
もっとも、これは大雑把にいってのことであって、人間の感覚と人間以外の動物の感覚とが全く同じだという訳では有りません。例えば、目(視覚器官)を持っているからといって、すべての目をもつ動物が人間と同じように物をみている訳ではなく、ある種の動物は色の区別を反映することができず、人間が白黒テレビをみている場合のように、明暗の差を区別できるだけですし、また、人間のように物の形をこまかく反映して、文字のような記考をその形によって正確に区別できる訳ではなく、物が動いているか静止しているかだけを区別できるに過ぎない、もっと正確にいえば、静止している場合には、ある物をその周囲にある他の物から区別することができず、その物が動く場合にだけ敏感にその運動(変化)を反映することができる動物も少なく有りません。
例えばガマ蛙はハエを食うのですが、目の前にある木の葉にハエが止まっていても、いっこうにこれを食べようとせず、そのハエが飛び立つと、その瞬間に長い舌を伸ばしてうまくこれを捕え、バタリと食べてしまいます。これは、ガマ蛙の目には、静止しているハエがみえず、動いたときにだけみえるからなのです。
また、鼻(嗅覚器官)が有っても、人間の嗅覚はそれほど鋭くなく、個人の特徴を匂いで区別することは、よほど特別な場合でないとできませんが、犬や象のような動物は嗅覚が鋭くて、嗅覚だけを頼りにしてさまざまな行動をすることができます。
このように各種の感覚器官の発達の程度は動物の種によって異なっているので、感覚器官による外界の反映の仕方も決して一様ではないのですが、しかしそれにもかかわらず、感性的段階の認識には、人間の場合にも人間以外の動物の場合にも、幾つかの共通点があります。
- その第一は、いうまでもないことですが、感覚器官に依存しているということです。
-
その第二は、その時その場所に現に存在している個別的な事物や状況を反映するものだ、と言うことです。
この講座の第7回に人間の意識の重要な特徴として、「一般化して反映する」という機能(働き)があることをのペましたが、感性的段階にある認識にはまだこの一般化するということができず、一つひとつの事物や状況をそのつど反映することができるにすぎません。 -
特徴の第三は、いまのベたことに密接に関連していますが、事物や事実の直接的な反映だ、ということです。
例えば、私が昨日おとした財布を拾ったとします。その時私は、拾った財布を目でみたり手で触ったりして(つまり、視覚や触覚を通して)感覚しているのであり、その限りではその財布を直接的に反映しているのですが、しかし同時に、それが昨日落とした財布であることを認識しています。
このことは、過去になんどもおこなった自分の財布についての感覚が記憶されていて、いまそれらの過去における感覚が記憶から呼び戻され、拾った財布についての現在の直接的な感覚と比較され、その同一性が確認されている、ということを意味します。
だから「これは昨日おとした財布である」という認識は、単なる事物の直接的反映ではなく、記憶によって媒介された反映であり、従って、感性的段階を超えた、それ以上の段階に達した認識である訳です。
このことを考えると、例えば犬が自分の飼い主とそれ以外の人間とを区別するということは、犬でも単に感性的段階に留まらない、それ以上の段階に達した認識をおこなうことができる、ということを示していることが分かります
さきに温度の例について述べたように、感性的段階の認識は誤りにおちいることが比較的多いのです。例えば「ゆうれいの正体みたり枯れおばな」という句がありますね。
これは、夜道をこわごわ歩いていてゆうれいだと思って逃げて来たが、翌日同じ場所にいってみたら枯れすすきだった、ということを皮肉にいったものですが、物の形がよくみえない夜ではなく、よくみえる明るい所でみても陥る誤りに錯覚というのがあります。
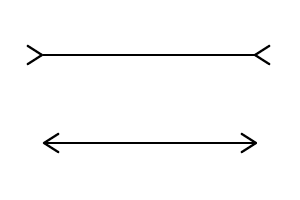
上の図では、ちょっとみると、上の線が下の線よりも長くみえます。
だが、ものさしをあてて長さを測れば、どららも同じ長さであることが分かりますこのような錯覚(視覚だけについていえば、錯視)をおこす図の例は、これらの他にもたくさんあります。
この場合に、ものさしをあててその目盛りをよむということも一つの感覚であるにちがい有りませんが、しかし、「ものさしで図った場合の方が線分の長さをいっそう正確に反映している」という判断は、もはや感性的段階の認識では有りません。
「理性的認識」
われわれは、ものさしを平行にずらせても、縦と横にその方向をかえても、その長さに変化が生じないということを、過去になんどもものさしを使った経験から知っているので、目でみた場合の直接的な感覚による認識よりも、ものさしで測って得た認識の方を正しいと考えるのです。
だからこの場合の認識は、過去の経験を媒介にしており、しかも過去の経験(これは有限回繰り返されたものに過ぎないのだけれども)を一般化しています。
このような認識を、理性的段階の認識というのです。
話を分かり易くするために、いまの例でも、前に述べたぬるま湯の温度を知ろうとする場合にも、ものさしとか温度計とかの道具(測定器具)を使う場合の例をあげましたが、理性的段階の認識は常になんらかの道具を使うという訳では有りません。
例えば、水の中に箸を斜めに突っ込むと、箸が水面のところで折れ曲がっているようにみえます。だが、指で箸をなぜてみると、箸は真っ直ぐであり、決して水面のところで折れ曲がっていないことが分かります
この場合には、視覚による反映と触覚による反映とが食い違っている訳で、これだけならば、視覚を信じてよいか、触覚を信じてよいか、分からないでしょう。
だが更に、箸を動かしてみると、折れ曲がってみえる位置が次々に移動しますし、水のなかからひき出せば、箸は真っ直ぐにみえます。箸のような固い物体が、次々にいろいろな位置で折れ曲がったり、真っ直ぐに戻ったりするのはおかしい、そんな筈はない、とわれわれは考える訳です。
こういう考えの基礎にも、箸に力を加えて折った場合に、それは折れたままで、もとのように真っ直ぐには戻らないということを、過去の経験を通してわれわれが知っている、ということがあるでしょう。
とにかく、われわれがこの場合に視覚ではなくて触覚による反映を、客観的事物(この場合には箸)のありのままの反映だと考えるのは、直接に感覚だけを頼りにしているのではなく(この場合には二種類の感覚が違った反映を与えるので、感覚だけに頼れば、どちらの感覚に頼ってよいか分からない)、過去の経験を媒介にして、そんな筈はないとか、こうである筈だとか考えている訳です。
このように、直接に感覚によって与えられているものではなく、何らかの他の知識を媒介として考える能力を理性(広い意味での理性)というので、このような認識を理性的段階の認識というのです。
他の本で「感性的認識」と「理性的認識」ということばに何回もであいました。そのように簡単にいわないで、わざわざ「感性的段階の認識」とか「理性的段階の認識」ということばづかいをしているのはなぜですか。
またいま、「理性」といって、すぐ「広い意味での理性」と言い直したのは、なぜですか。
もっと後で詳しく述べる積りなのですが、現在のわれわれ人間の認識には、純粋な「感性的認識」というものは有りません。その理由は、われわれ人間が既にことばを持っているからなのです。
第7回に「意識の役割」のところで述べておいたように、対象を一般化して反映するという意識の機能(働き)とことばとは密接に関係しています。
猿から人間へと進化する途上にあった原始的人類(あるいは猿人)の場合には、ことばが介入してこない純粋な感性的認識が有ったかも知れませんが、ことばを既に持っている現在の人類(われわれ)の場合には、感覚器官だけを頼りにして外界の事物を反映する場合にも、例えば目である物体をみれば、それは「石」だとか「木」だとかいうようにことばが結び付いてきますし、物体の色だけを反映する場合が仮にあるとしても(こういう場合はおそらく実際にはない。人間は色だけでなく形や大きさも同時に見てしまうから)、やはりそれは「赤い」とか「青い」とかいうようにことばが結び付いてきます。
ことばが結びつくことによって、個別的なものを直接的に反映している筈の感性的認識が、その時その場所に現にある個別的事物としてだけでなく、他のもろもろの石と同一性をもつ 「石」として、あるいは他のもろもろの赤い色と同一性をもつ「赤い」として、一般化されて反映されます。
従ってわれわれ人類がおこなう認識は、感覚器官だけに頼っているように思われる場合にも、上述のようにことばが介入することによって既に理性的な要素と結び付いているのです。
このような訳で、われわれ人類の認識について述べるさいに「感性的認識」という用語を用いて、純粋な感性的認識なるものを現に人類がおこなっているような印象を与えることを避けたいので、私はこの用語を用いず、「感性的段階の認識」というやや長い表現を使ったのです。 ―― ―― なお、認識とことばとの関係は、次回以後に詳しくとりあげます。
次に、人間の認識能力を区別する場合には、まずこれを大きく「感性」と「理性」との二つに分けます。これだけで話を済ませてしまう場合には、別にことわり書きを必要としません。
だが、立ち入って議論しようとする場合には、「理性」(広い意味の)を更に二つに分けて「悟性」と「理性」(せまい意味の)とに区別するのです。
同じ「理性」という用語が、感性と区別する場合には広い意味で使われ、悟性と区別する場合にはせまい意味で使われるので、話がややこしくなります。
「悟性」とはなにか、またそれと区別されるせまい意味での「理性」とはなにか、ということについては、この講座でもっとあとに詳しく述べるつもりでおります。
さてさきに、なんらかの他の知識を媒介として考える能力を(広い意味での)理性という、と述べました。このような意味での「考える」機能(働き)を「思考」といいます(かつては「思惟」といいましたが、「惟」という文字が制限漢字なので、このごろでは「思考」というのが普通です)。
日本語の「考える」ということばは漠然と広い意味に使われているので、哲学では困るのです。例えば、たんに「思い浮かべる」という場合にも、「あの日の出来事を考えると.........」などと申しますが、こう言う場合には哲学用語では「表徴する」と言います。
また、たんに自分個人の意見であって、他人がそれとは別の意見をもつだろうことをあらかじめ認めている場合にも、「私の考えるところでは.........」などと申します。こういう場合には哲学用語では「私念する」といいます。
これらの場合と区別して、ある問題にぶつかり、それを解決しようとして積極的に頭を働かせて考えることを「思考する」と言うのです。通俗的に「頭を働かせて」と申しましたが、ここで「頭」といっているのが、さきに述べた(広い意味での)「理性」に他なりません。
「表徴」だの「私念」だのということばは、見慣れない嫌なことばですが、漠然と「考える」といっている働きに三種類のものがあるので、それを区別するために、哲学ではこうした硬いことばを使わなければならないのです。
さて、ある問題にぶつかり、それを解決するために積極的に頭(理性)を働かせるのが「思考する」ということだと述べました。さきの例でいえば、箸が水面のところで折れ曲がっているという視覚による反映と、箸は真っ直ぐであるという触覚による反映と、どちらを信用するか、というのが問題であり、そこで思考することが必要になったのです。
これはいささか理論的な問題ですが、思考することが必要になるのは、なによりもまず実践的な問題についてです。
狩りによって野獣をとって生活していた時代の人類は、クマのような力の強い動物を殺すにはどうすればよいか、という問題について思考して、おとし穴をつくってこれにおとし、 相手側から攻撃されないような状態にしておいてから石槍でつき殺すことを考えたり、そばに近づかないで遠くからこれに攻撃を加えるために、投げ槍や弓矢のような飛び道具を考えだしたりしたのでした。
なんらかの実践的目的を達成するために、新しい道具を発見するということは、すべて人類が思考活動を行った結果であり、その結果得られた認識はすべて理性的段階の認識だった訳です。
ある種の動物もまた、生きてゆくため(主として餌をうるため)にある問題を解かなければならないという必要に迫られると、思考活動をおこない、その問題を具体的に解決することができます。
このような問題を解決するために、どの程度の思考を行うことができるかは、その動物の種がどの程度に高等な動物であるかを測る一つの指標だと考えられています。
動物の思考を調べる為に、チンパンジーやオランウータンを使っていろいろな実験がおこなわれていることは、本や映画によって御存じでしょう。
例えばチンパンジーは、天井から吊るされたバナナを取るために、箱を二つ積み重ねてその上に乗って取ることも、二本の棒をつないでそれで叩き落とすことも、考えつくことができることが、実験の結果として知られています。
ある種の動物が、意外に思われるほどの思考をおこなうということは、実験によってばかりではなく、かれらの実際生活上の行動によっても知られています。つぎのようなおもしろい実例があります。
北極地方の雪原に住んでいる白ギツネをとるために、人間が次のような仕掛けを考えました。
雪原上においた台の上に猟銃を水平に固定し、銃の後部に滑車をつけて、丈夫なひもの一端をひきがねに結び付け、そのひもを滑車を通して銃口の前面へ伸ばし、他端に肉を結び付けておくのです。
白ギツネが肉の匂いを嗅ぎつけてやってきて、肉をロにくわえてひっぱると、滑車を通したひもが引き金を引くので、銃口の前面にいる白ギツネは弾丸に撃たれて死ね、という訳です。
こういう仕掛けで始めのうちはうまく白ギツネを獲ることができたのでしたが、そのうちに、見回りに行くと、弾丸は発射されており、肉は取られているのに、白ギツネの死体はない、という奇妙なことが頻繁におこるようになりました。
白ギツネの思考が人間の思考を(少なくともこの仕掛けに関する限りでは)上回り 、人間は無駄に肉を白ギツネにごちそうすることになったのです。
では白ギツネは、この鉄砲仕掛けの肉を安全に取る為に、どんな方法を考えだしたのでしょうか。
驚くなかれ、白ギツネは、銃口の前にある肉のそのまた前の雪原の雪を掘って、自分の身体が入るだけの穴を作ったのでした。そして、穴の中に入り、口先だけを穴からだして、肉をくわえ、これを水平にではなく、下向きに引いたのです。
滑車を通したひもは引かれ、従って引き金も動き、弾丸は発射されます。しかし、その弾丸は穴の中にいる白ギツネの頭の上を通り越し、白ギツネは安全に肉を取って、「ごちそうさま!」という訳だったのです。
イソップ物語をよむと、キツネはしばしば悪がしこい動物としていろいろな話に登場してきますが、さきの白ギツネの知恵には、全く驚きます。
これは個体としての白ギツネが、自分の経験を通して学んだことでは有りません。
なぜかといえば、肉を水平にひいた白ギツネは、その場で弾丸に当たって死んでしまうからです。だから、かれらが学んだとすれば、それは他の個体の経験からだということになります。
仲間の白ギツネが弾丸に当たって死んでいるのをみて、銃口から水平に危険物がとび出すことを見抜き、穴を掘って自身の位置を低くし、下から肉を引けば危険がないと考えつくということは、相当な思考力だといわざるをえません。
白ギツネのような動物でも、これだけ高度の理性的能力を持っているのです(ただしこれは、悟性的能力であって、せまい意味での理性的能力では有りません。せまい意味での理性的能力は人間にだけあるのですが、このことについて述べるのは、もっと後に譲って、ここでは次の区別を述べておきます)。
具体的思考と抽象的思考・概念的思考
だが、どのように高度な思考を動物がおこなうにしても、それは人間の思考とは次の点で違っています。
それは、人間以外の動物の思考は、解決すべき問題が具体的状況として与えられており、従ってまたかれらの思考によって生みだされる解決の仕方も、具体的事物を使ってのかれらの具体的行動によるものだということです。
私はいまそれを人間として叙述しているので、人間のことばを使わざるをえません。
だから例えば、「チンパンジーは高いところにある餌を取る為に、箱を二つ積み重ねて踏み台にすることを考えついた」というように述べます。だが、ことばを持たぬチンパンジーにとっては、「高いところ」というような一般的状況はなく、実際に天井からバナナが吊り下げられている部屋の中に入れられた場合に、飛び上がっても手が届かないという個別的かつ具体的な状況があるだけなのです。
かれには、問題はこのように具体的に与えられなければならず、そこで初めてかれは、そのバナナを取るためにどうすればよいかを思考するのです。
そこでかれがおこなう解決も、実際に部屋の隅にある箱をバナナの真下へもってゆくという行動によって、一つの箱の上に乗ってもまだ届かなければ、もう一つの箱をその上に積むという行動によってのみ与えられます。
人間にとってならばこの場合に、問題は「高いところにあるものをどうやって取るか」というように、言葉を用いて一般化して与えることが出来ますし、解決も「踏み台に乗って取る」というように一般的に答えられます。
その場合に「踏み台」とは、箱でも机でも椅子でも、その上に自分が乗ってもつぶれないような、しかもある程度の高さのある物ならばなんでもよいのです。
このようにことばによって問題が与えられ、ことばを使って想考がなされ、解答もことばによって与えられるということが、人間の思考の特徴です。
人間の場合にも、問題が具体的状況によって与えられ、解決も具体的行動によって与えられることもあります。
例えば、ある人がある場所に監禁されたとき、その場で手に入るものだけを使って脱出する方法を考えた、というような場合はそうです。
だがこの場合にも、その状況と解決の仕方とは、脱出した人によってことばによって表現されることができるし、従ってまた一般化され、かれと同様の状況におかれた他の人によって同様の脱出方法として利用されることができるのです。
チンパンジーや白ギツネの場合にみられるような思考は「具体的思考」とよばれます。人間もまた具体的思考をおこないますが、人間は更に、ことばを用いて状況を一般化してつかみ、ことばを用いて抽衆的に思考することができます。このような「抽象的思考」のことを又「概念的思考」とも言います。
既に第8回に述べておいたように、概念はことばと結び付いていて、直接に感覚や知覚と結びつく必要がないからです。
概念的思考をおこなう能力を持つからこそ人間は、例えば、現存する社会体制を変革するにはどうすればよいか、というように抽象的かつ概念的に実践的課題をとらえ、これを概念を用いて理論的に解決することができるのです。
この点をいっそう明らかにするために、次回には「認識とことば」の関係について述べましょう。
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://y-ok.com/mt-tb.cgi/17
コメントする